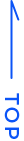-
A
場合により異なります。まず、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」は雇用保険の適用除外となり、加入の必要はありません。また、学生であっても、種類により適用除外となる人と適用される人がいます。
【適用される者(被保険者となる者)】 【適用除外となる者(被保険者とならない者)】 ・通信教育を受けている者
・大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者
・右記以外の昼間学生昼間学生のうち、下記の者
・卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
・休学中の者(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
・事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(社会人大学院生など)
・その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)その他の適用関係については、下記資料をご参照ください。
<参考資料:被保険者に関する具体例>(厚生労働省HP)
また、適用除外となる学生の詳細については、雇用保険法・雇用保険法施行規則・雇用保険に関する業務取扱要領
に記載されております。
————————
【適用除外】
<根拠法令:雇用保険法> 第6条
(適用除外)
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
三 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
↓
【厚生労働省令で定める者】<根拠法令:雇用保険法施行規則> 第3条の2
(法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
第三条の二 法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
一 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
二 休学中の者
三 定時制の課程に在学する者
四 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
↓
【職業安定局長が定めるもの】<参考資料:雇用保険に関する業務取扱要領>(職業安定局長が定めるもの) 16p 二
20303(3)被保険者とならない者
次に掲げる者は、法第6条等により、法の適用を受けない。したがって、適用事業に雇用される者であっても被保険者とならない
ニ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)
学校教育法(昭和26年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。ただし、昼間学生であっても、次に掲げる者は、被保険者となる。
(イ) 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
(ロ) 休学中の者(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
(ハ) 事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(社会人大学院生など)
(ニ) その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
Q 外国人留学生がアルバイトをする場合、雇用保険に加入しなければなりませんか?
同じカテゴリの人気Q&A
-
現在の在留資格(身分系在留資格を除く)で3か月以上、その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが、「正当な理由」があれば取消対象とならないと聞きました。「正当な理由」とはどのような場合が該当しますか?
-
入管庁の書類の保管期限はありますか?
-
特定技能で自動車運送業が新たに産業分野に追加される予定ですが、自動運転に免許は必要ですか?
-
外国人雇用のセミナーに参加した際、トライアル雇用助成金、キャリアアップ助成金などの助成金制度があると聞いたのですが、助成金にはどのようなものがありますか?
-
入管に電話しても中々つながりません。忙しいのは分かりますが、そもそも入管の内部での業務分担はどのように決められているのでしょうか?
-
転居を伴う配置転換に応じられることを昇給の条件にしても問題ないでしょうか。
-
外国に家族がおり、日本から仕送りをしています。令和5年1月より、年間38万円以上支払っていないと所得税の扶養控除が受けられないと聞きましたが、本当ですか?
-
現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在住していますが、日本人の特別養子となる予定です。この場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更は認められますか?
-
自社で雇用中の外国人が労災に遭いました。労働局や入管など関係省庁への必要な手続について、教えてください。
-
上陸特別許可と在留特別許可の違いは何ですか?
- 01 雇っている特定技能外国人が突然いなくなりました。失踪届等、行うべき入管上の手続きはありますか?
- 02 特定技能外国人が退職することになりました。入管への手続きは何か必要ですか?
- 03 特定技能外国人は、賞与、昇給がないといけないでしょうか。
- 04 参考様式第5-6号「定期面談報告書」に、監督者と記載がありますが、この監督者とは誰でも良いのでしょうか。
- 05 どのような場合に在留資格が取り消されますか?
Q&Aランキング
- 01 外国人が自転車事故にあってしまった場合、どのように対応すべきでしょうか?
- 02 外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
- 03 現在の在留資格(身分系在留資格を除く)で3か月以上、その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが、「正当な理由」があれば取消対象とならないと聞きました。「正当な理由」とはどのような場合が該当しますか?
- 04 外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?
- 05 令和6年4月に技能実習の運用要領が改訂されたそうですが、重要な改訂ポイントを教えてください。




 " alt="【行政書士と社会保険労務士が徹底解説】外国人就労トラブル/入管法違反を紐解く">
" alt="【行政書士と社会保険労務士が徹底解説】外国人就労トラブル/入管法違反を紐解く">
 " alt="【外国人ドライバー解禁!!】特定技能 自動車運送業徹底解説~制度の重要なポイント/免許試験対策/人材募集まですべての要素をご説明します~">
" alt="【外国人ドライバー解禁!!】特定技能 自動車運送業徹底解説~制度の重要なポイント/免許試験対策/人材募集まですべての要素をご説明します~">
 " alt="【現場の教育課題を解決!】多言語化する現場で安全・品質・生産性を担保するための具体的教育手法">
" alt="【現場の教育課題を解決!】多言語化する現場で安全・品質・生産性を担保するための具体的教育手法">